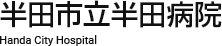血管外科
概要・方針
高齢者の増加と診断技術の発達により、動脈硬化に起因する血管疾患は増加傾向にあります。心筋梗塞、脳梗塞は主に動脈硬化による血行障害を生じた病気で、日本においては死因の上位にあります。
動脈硬化は心臓や脳だけでなく全身におこり、下肢に生じた場合は歩行障害などをきたします。下肢の血行障害を改善すると、日常的な症状改善はもとより、他の血管疾患に伴う病気の余命を改善すると考えられています。
当院血管外科では脳、胸部以外のすべての血管(動脈、静脈)を扱います。かかりつけの医療機関で血管疾患ではと診断された方、ご自分で今の症状が血管の病気からきてるのかも知れないと心配されている方の診療を行っています。
また、当院は救命救急センターにて、血管外科領域の緊急疾患(腹部大動脈瘤破裂、急性動脈閉塞など)に対しても24時間体制で対応しています。
動脈硬化は心臓や脳だけでなく全身におこり、下肢に生じた場合は歩行障害などをきたします。下肢の血行障害を改善すると、日常的な症状改善はもとより、他の血管疾患に伴う病気の余命を改善すると考えられています。
当院血管外科では脳、胸部以外のすべての血管(動脈、静脈)を扱います。かかりつけの医療機関で血管疾患ではと診断された方、ご自分で今の症状が血管の病気からきてるのかも知れないと心配されている方の診療を行っています。
また、当院は救命救急センターにて、血管外科領域の緊急疾患(腹部大動脈瘤破裂、急性動脈閉塞など)に対しても24時間体制で対応しています。
診療内容と特色
腹部大動脈瘤(AAA)
腹部の大動脈の疾患である腹大動脈瘤について説明します。動脈瘤とは、動脈が拡大している(ふくらんで大きくなっている)状態で、その多くは自覚症状がありません。ほとんどが検診や他疾患の検査でのCT、超音波などの検査をした際に発見されます。症状が無いため発見されずに、知らないうちに大きくなっていることは珍しくありません。
動脈瘤は大きくなればなるほど破裂する率が高まります。大動脈瘤はいったん破裂してしまうと、急激なショック状態に陥り、たとえ手術が行えたとしても死亡率が非常に高くなります。そのため、動脈瘤と診断がついた場合は、破裂する前に切除して人工血管に取り換える手術を行います。最近では、何度も腹部の手術をしたことのある方や全身状態の悪い方には血管の中から人工血管を内挿するステントグラフト内挿術という治療も行えるようになってきました。
動脈瘤は大きくなればなるほど破裂する率が高まります。大動脈瘤はいったん破裂してしまうと、急激なショック状態に陥り、たとえ手術が行えたとしても死亡率が非常に高くなります。そのため、動脈瘤と診断がついた場合は、破裂する前に切除して人工血管に取り換える手術を行います。最近では、何度も腹部の手術をしたことのある方や全身状態の悪い方には血管の中から人工血管を内挿するステントグラフト内挿術という治療も行えるようになってきました。
下肢静脈瘤
下肢静脈瘤につきましては、当院では診療を行っておりません。
その他
急性動脈閉塞、レイノー症など
診療実績
| 令和4年度 | 令和5年度 | |
| 腹部大動脈瘤手術 | 13 | 11 |
| うち、破裂緊急手術 | 1 | 4 |
| その他の動脈手術 | 1 | 3 |
| 下肢静脈瘤手術 | 7 | 6 |